新潟県上越市の直江津小学校で、児童が漂白剤を含む水を飲むという事故が発生しました。この事故は2025年5月12日に起き、小学1年生から6年生の児童6人が誤って消毒用の水を口にしてしまいました。
児童たちはすぐに「苦い」「プールのような味がする」と異変を訴え、学校側が救急搬送を決定。搬送された6人の児童は病院で検査を受けたが、幸いにも健康に大きな影響はなく、経過観察のため入院していた1人もすでに退院しました。
この件は、学校での安全管理が問われる重大な事故であり、保護者や地域住民の間でも関心が高まっています。
事故の原因は?教頭の判断ミスだけではない?
今回の事故は、教頭の誤認によって引き起こされたものではありますが、それだけではなく、学校の連携不足が背景にあったことが判明しているようですね。
事故当日、用務員が飲料タンクに水を張り、別の教員が塩素系漂白剤を入れて消毒を行っていたようです。しかし、その水が消毒中であることを明示する表示がされていなかったため、教頭が飲料用の水だと思い込み、児童が飲めるように配置してしまったということです。
さらに、タンクを設置する前の確認作業が十分に行われなかったことも問題点として挙げられます。通常ならば、消毒作業を行った教員とタンクを設置する教員の間で情報共有が必要でした。しかし、今回はその連携が不十分だったため、誤飲事故に至ってしまいました。
このような管理体制の不備を受け、市教育委員会は今後、
- 消毒水の明確な表示の徹底
- 設置前の確認作業の義務化
- 教職員間の連絡体制の強化
といった再発防止策を検討しているようです。しかし、具体的にどのような形で実施されるのかは未定であり、引き続き慎重な対応が求められます。
保護者の不安と地域の声
この事故が起きる約3週間前には、上越市の別の小学校で給食に蛍光灯の破片が混入する事故も発生していました。この連続したトラブルは、市や学校の安全管理体制に大きな課題があることを浮き彫りにしています。
事故発生後、SNSや地域の保護者の間で不安の声が広がっています。多くの保護者が「学校は安全だと思っていたが、こんな事故が続くと信用できない」「対策はどうなっているのか」といった懸念を示しています。
ある保護者は「子どもが口にするものにもっと慎重になるべき。学校だけでなく、市全体で安全管理の意識を持ってほしい」と話しています。
児童たちの健康被害は軽度だったものの、学校の管理体制を問う声は強く、上越市全体で再発防止策を早急に進めることが求められています。
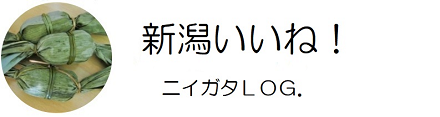





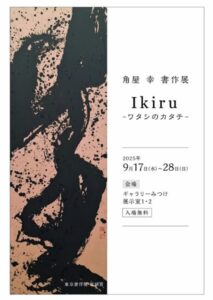
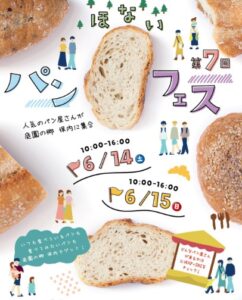



コメント