2025年9月10日、新潟県内で前日からの断続的な豪雨により、各地で道路冠水や越水が発生。長岡市、新発田市、三条市などでは住宅地や幹線道路が広範囲に水没。新発田市では土砂災害の危険性が高まり、261世帯に避難指示が出されました。
報道映像やSNSの動画では、冠水した道路を走行する車両が多数映し出され、SNSでも「どこまでなら走っていいのか」「車内に水は入るのか」といった不安の声が広がりました。新潟県は公式に「冠水路への侵入は避けるように」と注意喚起を行っており、今後も同様の気象状況が予想される中、車の水没限界についての正しい知識が求められます。
車はどこまで水に浸かると危険?構造と水位の関係
国の機関・業界団体・専門メディアが一致して警告している実証的な基準にもあるように、車両は水深30cmを超えると重大な故障や安全上のリスクが高まります。
国土交通省は「床面を超える水位は危険」と明示し、JAFの冠水走行テストでは水深60cmでエンジンが停止。自動車情報メディアも、電装系の故障や車内浸水のリスクを30cm前後から指摘しています。
以下は水位ごとの影響と故障リスクです。
| 水位の目安 | 車体への影響 | 故障リスク |
| タイヤの半分以下(~20cm) | 比較的安全 | ブレーキ性能低下、マフラー腐食 |
| タイヤの半分以上(~30cm) | マフラー浸水 | エンジン停止、電気系統ショート |
| ドア下端以上(~40cm~) | 車内浸水開始 | カビ・異臭、電装品故障、脱出困難 |
車内に水は入る?小さな穴からの浸水リスク
- 車の床下には排水穴があり、通常は水を外に逃がす構造ですが、冠水時には逆流して車内に水が侵入することがあります。
- 水圧が高まるとドアが開かなくなることもあり、乗員の安全確保が困難になります。
- 特にハイブリッド車やEVは床下に電装系が集中しているため、早期故障や感電リスクも。
冠水時の走行で起こる主な故障
- マフラー浸水:排気できずエンスト
- 吸気口浸水:ウォーターハンマー現象でエンジン破損
- 電気系統ショート:火災や走行不能
- 車内浸水:カビ、異臭、内装劣化、廃車判断
水没は「走れるか」より「戻るか」の判断を
9月10日の新潟のような冠水状況では、渋滞を気にして進むより、引き返す判断が命を守ります。水深30cmを超えると、車は構造的にも安全面でも限界を超えます。迷ったら、戻る。これが最も確実な選択です。
 新潟いいね!
新潟いいね!冠水路では「走れるか」ではなく「戻るか」で判断を。水深30cm以上はエンジン停止や車内浸水のリスクが高く、ドアが開かなくなることもあります。9月10日の新潟のような豪雨時は、無理な侵入を避け、冷静に引き返す判断が命と車を守ります。
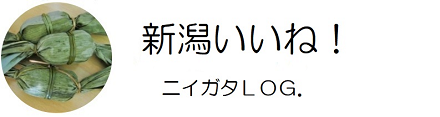







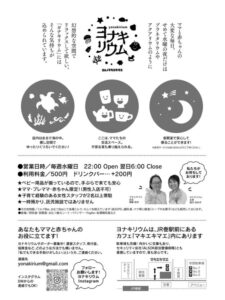



コメント