新潟県上越市の中川市長が、兵庫県三田市産の米に対して「まずい」と発言したことが大きく報道されました。その後、謝罪と試食を経て「本当においしい」と評価を改めたことで、事態は収束へと向かいました。
でも冷静に見てみると、市長が語ったのは「子供時代に食べた米」の記憶でした。つまり、「米がまずい」のではなく、その時の家庭での保存・炊き方・時間経過などがたまたま悪かった(それが三田市産米ではなかった場合も)。という可能性が大いにあるのです。
一瞬の条件で「味の印象」は大きく変わる

- 保管場所が高温多湿で、米が劣化していた
- 炊飯器の性能や水加減が最適ではなかった
- 何時間も経って冷め・保温していて、食感が悪くなっていた
実際、「まずい」と感じたその瞬間は、こうした一時的な要因による可能性が高いと考えられます。
米農家が育てたお米は、本来“美味しい”
三田市のお米も、丹精込めて作られた地域の誇り。市長自身も謝罪の場で試食し、「本当に美味しい」と評価を一変させています。
つまり、“米がまずい”という印象は、誤った条件での経験による一時的なもの。米の品質そのものではなく、記憶の中で生まれた誤解だったのかもしれません。
誤解をほどく視点が、食への理解を深める
たった一言が波紋を呼ぶ時代だからこそ、「なぜその印象になったのか?」と丁寧に見つめ直すことは、食の価値や背景に目を向ける大切な機会になります。
 新潟いいね!
新潟いいね!発言された「米がまずい」という印象は、米の品質そのものではなく、保存・炊飯・経過時間など一時的な条件による可能性が高いといえます。米本来の味を誤解なく評価するには、記憶や状況を丁寧に振り返る視点が大切です。
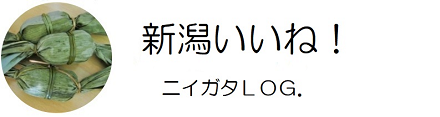

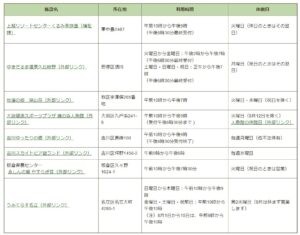









コメント